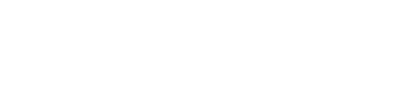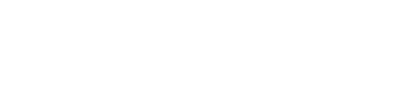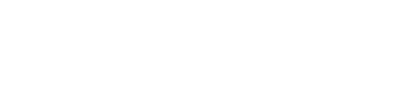 【2018-09-21 20:18 pm 歌舞伎町】
【2018-09-21 20:18 pm 歌舞伎町】
マップアプリに表示される現在地は、数秒おきにブレ続けていた。
もはや頼りにならないGPSを無視して、地図上の交差点名だけを頼りに、慎重に脇道の数を数えていく。
高層ビルに囲まれた、細い路地。
住所によれば、目的地はこの先のはずなのだが、
こんな裏通りに、本当にあるのだろうか。
戸川愛理は思わずそこで足を止めてしまった。
飲食店の裏口が並んでいるせいか、表通りよりも数段蒸し暑さを感じる。
中華とイタリアンの匂いが左右の換気口から吹き出してきて、もはやカオスだ。
先に進むか否か、しばし考え込んでいた彼女の脇を、ひとりの青年がすり抜けるようにして追い越していった。
白のロングTシャツの袖を無造作にたくし上げた彼は、黄色いドラムバッグを肩にひっかけたまま、通りの奥へと向かっていく。
すれ違いざまふわりと漂ってきたのは、意外にも洒落たムスク系の柔軟剤の香りだ。
後姿は学生にも見えるが、この時間帯の歌舞伎町にはあまり似つかわしくない気もする。
彼が何者なのかちょっと気になって、追いかけるようにして愛理も路地へと足を踏み入れた。
GPSは相変わらずブレている。
一度マップ上に表示されているピンの位置を確認して、再び顔を上げると、
いつの間にか前を歩いていたはずの青年の姿が消えていた。
通りは一本道で、入り込めそうな脇道などない。
微かにどこかで、カラン、というドアベルの音が響いた気がする。
あたりを念入りに見回し、愛理は「あぁ」と溜息のような声をあげた。
ダイニングカフェ『INANIS』。
その店の看板は半分地下に埋まるようにして、ひっそりと灯りをともしていた。
隣のビルの空調の室外機から吹き出す熱気を浴びながら短い階段を下って、
半地下の高さにあるレトロなデザインの扉をぐっと引く。
見た目以上に重たい扉が開くと、ひんやりとした風が吹きつけてきた。
店内に入って真っ先に目に入るのは、両手で抱えられるくらいのサイズ感の、ガラスケースだ。
入り口正面のラックに飾られたそれは、控えめなライトを浴びてキラキラと光っている。
何も入っていない、空っぽのガラスケース。
それが、この店の象徴だった。
ドアベルの乾いた音に気付いて、カウンターの中でコーヒーを淹れていた女性店主が顔を上げる。
「いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ」
やわらかなソプラノはどこか、AIの合成ボイスを彷彿とさせた。
店内はカウンター席と3つのボックス席のみという、こじんまりとした構造になっている。
客は、愛理の他に、ひとりだけ。
一番奥のボックス席。入り口に背を向けるようにして腰を落ち着けていたのは、先ほどの青年だった。
控えめな照明のため若干薄暗い店内に、彼の手元のスマホの画面が青白く浮かび上がって見える。
愛理は少し考えて、入り口近くのカウンター席に腰を下ろした。
店主のほっそりとした指先が、音もなくコースターを差し出し、レモンの浮かんだフレーバーウォーターのグラスが置かれる。
「もうすぐラストオーダーのお時間なんですけど、ご注文はいかがなさいますか?」
「えっ・・・まだ8時過ぎですよね?こちらのお店って、閉店時間、早いんですか?」
少し驚いて、愛理は問い返してしまった。
眠らない街、歌舞伎町にあって、この時間にもうラストオーダーとは、いったいどういうことなのか。
「すみません。ちょっと事情があって・・・うちは21時クローズなんです」
店主が本当に申し訳なさそうな顔をするので、愛理は慌ててかぶりを振った。
「いえ。むしろ間に合ってよかったです」
重たい扉が外の喧噪をシャットアウトしているのか、店内は別世界のように静かだ。
耳をそばだてると、ほんの微かに、FMラジオのような音声が聞こえてくる。
少しこもったその音を鳴らしているのは、カウンターの奥に無造作に転がっている小さなラジカセのようだった。
ラジカセ。今このご時世に。
なんだか不思議な心持ちで愛理はメニューを手に取る。
年季の入ったアルバムタイプのメニュー。
表紙を開こうとしたが、やめた。注文するものは、最初から決まっている。
「フェアリーテイル、ありますか」
3割の期待と、7割の猜疑心とをもって、愛理は店主にそう告げた。
彼女は、おっとりとした微笑みを浮かべて、ちいさく頷く。
拍子抜けするほどあっさりと注文が通ったのと同時に、何故か店の奥から、息をのむ気配を感じた。
店主が棚から取り出したのは、パステルブルーの小さな缶だった。
手早く湯を沸かし、アンティークなティーポットとカップを温める。
フェアリーテイルというのは、どうやらお茶のことらしい。
目の前でカップに注がれた紅茶は、澄んだ琥珀色をしていた。
ベリー系だろうか、茶葉をおさめていた缶の色とはちぐはぐな、フルーティーな香りがする。
カップの横に温めたミルクを置くと、店主がカウンター越しに、そっと顔を寄せてきた。
内緒話をするみたいに口元に手をあてて、悪戯っぽく囁く。
「フェアリーテイルが冷める前に話しかけると、新宿の妖精さんが、助けてくれるかもしれませんよ」
からかうような口調とは裏腹に、紅茶と同じ色をした彼女の瞳は、戸惑うほどに真剣だった。
———新宿の妖精さん。
そんなふざけた言葉を最初に聞いたのは、事務所の先輩からだった。
半信半疑でここまで来て、なかば捨て鉢な気分で注文したのだが、
逆に言えば、それほどまでに、愛理は思い悩んでいた。
まだ熱いティーカップを、両手でそっと持ち上げる。
立ち上る湯気が、エアコンの冷風に掻き乱されている。
迷っている時間はないのだと、愛理は悟った。
「———人を、探しています。私のとても、大切な人を」
当然ながら、紅茶は何も答えない。
愛理はカップを一度置くと、バッグから一枚の写真を取り出した。
「遠野さゆりさんといいます。私にとっては、母の妹・・・叔母に当たる人です。
この写真は10年前のもので、現在の年齢は31になります———彼女がもし、生きているのなら」
カップの隣に写真を並べて、愛理はさらに一冊の本を、その隣に置いた。古いハードカバーの本だ。
「10年前、彼女は駆け出しの女優でした。
当時あらゆるジャンルのオーディションをひたすら受けていた彼女は、
幸運にも初めて映画の主演に抜擢されて———これが映画の原作本なんですけど」
日焼けにより劣化した本の表紙には、『青の夢』というタイトルが踊っている。
それは愛理が子供の頃、本屋さんの店頭で平積みになっていたベストセラー小説だった。
「撮影が始まって、一週間ほど経った頃———彼女は突然、失踪しました」
失踪、という言葉を口にするとき、少しだけ声が震えたのを自覚した。
カップに触れる。さっきより、ずいぶんぬるくなってきている。
「主演女優の失踪というトラブルによって、映画の制作は頓挫しました。
それが今年、どういうわけかキャストを一新して再制作されることになったんです」
胸のあたりが、ざわざわする。
紅茶は何も答えない。琥珀色の液体はゆったりと揺れて、愛理の話の先を促しているみたいだった。
「かつての主演女優の安否も分からないのに。
彼女の身に何が起きたのかも、未だに何も分からないのに。
それが、どうしても納得できなくて———私、事務所の先輩に無理なお願いをして、再制作版の、役をもらいました」
カップはどんどん冷めていく。
両掌はもう熱さを感じていなくて、ほのかな温もりがそこに残っているだけだ。
「私、さゆりさんのことが大好きでした。
大好きな叔母様で、お姉ちゃんで———憧れの、女優さんでした。
彼女が今どこにいるのか、10年前に何があったのか、私は知りたい」
鼻の奥がつんとして、自分が今、泣きそうになっているのだということに気付いた。
ぬるくなってしまったフェアリーテイルを、ひといきに飲み干す。
砂糖も入れていないのに、何故か優しい甘さが口いっぱいに広がった。
お茶はおまけで、本題は妖精さんのほうだとばかり考えていたので、
思いのほかフェアリーテイルが美味しかったことに、愛理は少しだけ動揺した。
「・・・あの、メニュー見ないで注文しちゃったんですけど、このお茶のお代って」
ひょっとして、おまけのない一杯だったとしても、相当な高級茶葉なのではないだろうか。
少しばかり不安になっている愛理に、店主はふわりと微笑んでみせた。
「それのお代は、願い事が叶った時にだけいただく約束なんです。・・・妖精さんとの」
代わりにこれを、と、下げたカップと入れ替えに、
ジェラートが山盛りに盛られたパフェグラスを差し出される。
「今日、暑かったから、作りすぎちゃって。食べて行っていただけると、助かります」
立地に見合わぬ良心価格のジェラートをたいらげた客が店を去ったのは、
21時———閉店時間ちょうどのことだった。
この店の店主で唯一の店員、常盤環は、看板の灯を消しに一旦店の外へ出る。
少し肌寒いくらいの店内には、客の一人だけが取り残されている。
空になったピラフの皿をテーブルの脇に追いやって、彼はぼんやりと天井を見上げている。
と、店内に微かに響いていたラジオの音が、唐突に乱れた。
何か強い電波に妨害されるような、耳障りなノイズが数秒続いて、また唐突に、静かになる。
『———さっきの依頼、断らないよな?』
電波越しのその声がくぐもっているのは、単純にラジカセのスピーカーが安物だからだ。
「無理」
日吉幸名は天井を見つめたまま、短く返す。
『なんで』
「俺が”妖精さん”じゃないから」
『ケチだな』
「そういう問題じゃない。10年も前のことを、素人がどうこうできる気がしない」
『妖精さんに、時間の概念なんて無いでしょ』
「だから、俺は”妖精さん”じゃない」
すっかり面倒くさくなって、幸名は冷めてしまったアメリカンコーヒーに口をつけた。
ほぼ同時に、テーブルの上に放られていたスマホの通知音が鳴る。
メッセージアプリに貼り付けられていたのは、古い週刊誌の記事の写しのようだった。
『お前、さっき一度も振り返らなかったけど、もしかして、客の顔、見なかった?』
「見てない。つーかそっちは、この店の中ずっと覗いてたわけ?」
『ずっとは見てない。珍しい注文が入ったから、興味本位でそこから』
開店当時から客の入りが極めて少ないこの店に、
女性店主一人じゃ何かと危ないからと防犯カメラを取り付けたのは、このビルの最上階に住む住人だ。
ガジェットオタクでもある彼にとって、防犯などというのは単なる口実で、
実のところは、最新型のマイクロカメラを他人の金で購入して遊びたかっただけなのである。
『でも、話は聞こえてただろ。彼女の”声”は』
「———声?」
そう言われれば、最近どこかで聞いたような気がする。
よく通る、どこか意思の強そうな、独特の———・・・
『”昼間”に会っただろ、あの子と』
「———あ。」
とてつもなく嫌な予感がして、幸名は黄色いドラムバッグの中身を漁った。
昼間、アルバイト先で半ば強引に押印を迫られた契約書類と引き換えに押し付けられた、資料の束。
1枚目の紙に大きな文字で記載された、企画書、という三文字以外、
中身はおろか、表紙すらロクに確認していなかった。
どちらかといえばポーカーフェイスと言えなくもない幸名の顔に、
珍しく、焦りの色が浮かんでいる。
さっきの客がカウンター席に置いていった古い書籍の表紙と、
手元の紙束の表紙を見比べる。
絶望した。
再制作版「青の夢」企画書。
「あの客、まさか、戸川愛理———・・・」
唸るような声が漏れてしまった。
アルバイトはあくまでもアルバイトなのであり、
幸名の本業は、ごく普通の怠惰な大学生である。
無論、妖精さんでも何でもない。正真正銘、ただの人類だ。
『で、さっきの依頼、断らないよな?』
電波の向こうの声は、明らかにこちらを煽っていた。
モニター越しに、頭を抱える幸名を眺めながら、ニヤニヤしているに違いない。
基本的に暇なのだ、あいつは。
幸名は、深い、深い溜息をついた。
「断らないんじゃない。この依頼、俺には断れない・・・」