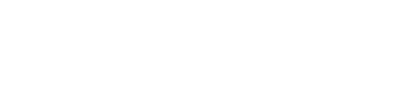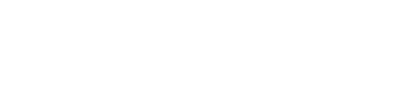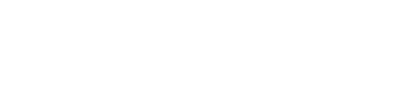 「・・・・・・っ痛・・・」
「・・・・・・っ痛・・・」
スニーカーの靴紐を結んでいた鹿目空は、そのままぐったりと蹲った。
腹が痛い。ここのところ、毎朝。
「・・・ソラ?」
玄関先で動かなくなった空に気付いた母親が、溜息をつく。
「またお腹が痛いの?ちゃんと検査もしたし、お医者様も悪い病気じゃないって言ってたわよね?」
分かっている。この腹痛の原因は、ただのストレスだ。
腹が痛いからといって、病気でもないのに学校を休むのは、ただの甘え。
「・・・・・・・・・いってきます」
さし込むように痛む腹を抱えて、空は家を出る。
———この世界は、地獄だ。
ぱんぱんに荷物を詰め込んだバックパックが、空の足を重くさせる。
教科書、ノート、運動着、———それから、上履きと、英和辞典。
クラスのみんながロッカーに置いて帰るものも、空にはそれができない。
翌朝には、ぐちゃぐちゃに汚されているか、なくなっているからだ。
かろうじて持ち帰ることができるものはいい。
先週には、とうとう、登校したら、空の席の、椅子がなくなっていた。
さすがに机と椅子は持ち歩くことができない。
仕方なく、空き教室から一脚拝借して、今日までどうにか騙し騙し過ごしてきたのだが。
「勉強っていうより、筋トレだな・・・」
長い坂道を上っていると、いよいよ腹の痛みが増してくる。
この門をくぐったら、その先は、戦場だ。それか、地獄。
どこから何が落ちてくるか、どこで何をされるか、分からない。
登校するだけで食らわされる罰ゲームのバリエーションは無限だ。
校舎から漂う負のオーラは異常———だが、空は負けない。あと少し登校すれば、卒業式を迎えることができる。
来月からは、この学校の生徒が一人もいない、遠方の高校へ進学できるのだ。
「大丈夫、大丈夫・・・気にしすぎない。不安がらない」
そう自分に言い聞かせて、教室の引き戸を開ける。
窓際、後ろから2番目の机の上には、
「———無理ィ・・・」
バレンタインチョコの抜型いっぱいに、虫の死骸が、詰め込まれていた。
そんなこんなで、空はようやく地獄の中学三年間を踏破した。
高校デビューもそこそこ成功、というか、失敗することなく、半月が経過しようとしている。
前の席の男子生徒に「おはよう」と言われたときはさすがに感動してしまって、ちょっと泣いた。
ロッカーに辞書を置いて帰っても破かれないし、上履きもなくならない。
長いこと空を悩ませていた腹痛も、いつの間にか完全に消えていた。
毎朝電車で1時間以上かかる通学時間に目をつむれば、何一つ不満も不自由もない、そんな生活だった。
———その日の、朝までは。
ぎゅうぎゅうの電車から、同じ制服を身に着けた学生たちが大量に吐き出される。
そのまま流されるようにして改札を押し出されたとき、ふと、懐かしい感覚にとらわれた。
突然に、引き攣れるような痛みが、空の腹を襲う。
景色が歪む———駅前の、見慣れた景色に変わりつつある光景が、くすんだ色に見える。
その景色の端っこで、唐突に、赤い色がはじけた。
「———!?」
一瞬遅れて、あちこちから甲高い悲鳴があがる。
斜め前を歩いていた同じ制服が、ぐらりと傾ぐ。
倒れた少年を中心に、くもの子を散らすように人々が逃げ出す。
人が、刺された。
現実はシンプルに、ただそれだけのことだ。
けれどそれは、どこかディスプレイ越しのような、非現実さを感じさせる。
凶悪な光を放つ刃物を握り締めていたのは、同じ制服を着た、昏い瞳の少年だった。
彼は何かを叫んでいる。死んだ魚のような双眸からは、止めどなく涙が溢れ続けていた。
空は、動けない。
彼が何を訴えているのか、理解することを、脳が拒んでいた。
少年が、返り血で真っ赤に染まった腕を、再び振りかざす。
けれど、彼がそれを振り下ろすことはなかった。
いつの間にそこにいたのか、一人の少年が、彼のすぐ後ろから、鮮血の滴る手首を無造作に掴んでいる。
どちらかというと華奢な腕が、流れるようにしなって、振り上げていた腕を後ろ手に拘束する。
なおも抵抗する少年の耳元で、彼は何かを囁いた。
ほんの短い、センテンスで。
少年は、涙と返り血でぐちゃぐちゃになった顔で、空を仰いだ。
拘束された手から、刃物が落下する。
騒ぎを聞きつけたのか、ようやく校門に常駐している警備員たちが駆けつけてきた。
今はもう抵抗する様子もない加害者が、警備員へと引き渡される。
警備員に拘束された彼は、一瞬立ち止まって、力無く振り返る。
———目が合った、ような気がした。
うっそりと、満足げにその唇がつりあがる。
彼は何かを呟いた。
何と言ったのか、聞き取ることはできない。
けれど空には、彼の声が、聞こえたように思えた。
彼が見上げた蒼空を、追いかけるように見上げる。
吐き気がするほど青く、どこまでも澄み渡った、春の空だった。
ごく普通の高校生による殺傷事件はマスコミによって大々的に報道されたが、
その熱もほんの数日ですぐに冷めた。
あの加害者の少年は、被害者によって長く虐め抜かれていたらしい。
ふたを開けてみれば、驚くほどシンプルな事件だった。
そんなこんなで、今朝のワイドショーは、大物俳優の不倫騒動で盛り上がっている。
そして空はというと、
あの日を境に、外へ出かけることができなくなってしまっていた。
毎朝ちゃんと、同じ時間に起きて、制服に着替えて、玄関で靴を履く。
靴紐を結んでいると、猛烈に体調が悪くなる。
昔と違っているのは、母の対応だ。
事件を間近で目撃してしまったことによる精神的ショックについて、
担任やその他えらい大人たちからあれこれと吹き込まれたらしい。
靴を放り出してトイレへ駆け込む空を、彼女はとがめなくなった。
この世界は、地獄だ。
人は簡単に、変われない。
変われないけれど、踏み外すのは思いのほか簡単なのだと、思い知らされた気分だった。
「———ソラ。お友達が来てくれたわよ」
夕方、ふとそんな声が自室のドアの向こうから聞こえてきた。
ぼんやりとSNSを眺めていた空は、彼女の言葉の意味がよく分からないまま、寝転がっていたベッドから起き上がる。
階段を降りて、玄関を覗くと、ひどく印象の薄い少年が立ち尽くしていた。
10秒くらい考えて、ようやく彼がクラスメイトであることに思い至る。
確か・・・日吉、といったか。友達と呼ぶにはあまりに接点がなさすぎる距離感の、クラスメイト。
彼はこちらに気付くと、申し訳無さそうにはにかんだ。
「なんか、俺でごめん・・・」
ちょっと頼り無さそうなその表情に、空の中の警戒心が薄れていく。
「や、こっちこそ、わざわざ来てもらって・・・」
恐縮する空に、日吉は一冊のノートとクリアファイルを手渡した。
空が学校を休んでいた間の、講義ノートと課題のプリントらしい。
「こっちは担任から預かったやつ。で、あとこっちが・・・」
パステルイエローのドラムバッグを日吉がごそごそと漁る。
華やかなバッグは、本人のイメージとは少しそぐわないデザインのような気がした。
「俺ん家の上の部屋の契約書、大家さんから預かってきた」
「・・・・・・ん?」
唐突な申し出に、空は首を傾げる。契約書とは。
こちらが戸惑うことも想定内なのだろう、日吉はちいさく苦笑した。
「鹿目に似たやつ、何人か知ってる。うち、そういうやつが引っ越してくるのにちょうどいい物件だから」
ふう、と息をついて。
彼は、囁くように告げる。
「無理に戦わなくたっていいし、外に出なくても、学校に行けなくてもいい。
———蜘蛛の糸は、どこかにあるよ」
手渡された封筒には、宛名は書かれていない。
裏返すと、送り主の名前の代わりに、銀色のペンで、細い線が一本、縦に引かれているだけだった。
蜘蛛の糸。
地獄のようなこの世界のどこかに、それがあるなら。
すがってもいいのだろうか。
「また来週、プリント届けに来るから。
気が向いたらその時にでも、返事聞かせて」
日吉は顔の前でひらりと手を振って、玄関のドアに手をかけた。
一瞬開いたドアから、夕暮れの光が差し込んでくる。
オレンジ色の———どこか懐かしい色をした空が、瞳の奥に焼きついた。