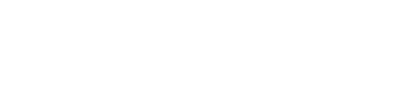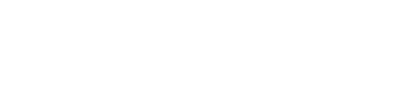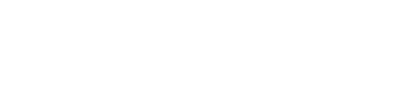 しあわせというのは、訪れるのも突然だが、失われるのもまた、突然だ。
しあわせというのは、訪れるのも突然だが、失われるのもまた、突然だ。
幸名にとってのちいさなしあわせは、たった一枚の張り紙によって、失われてしまった。
『しばらく おやすみします。』———そんな短い、文章ひとつで。
その駄菓子屋は、まぁるいメガネをかけた、少しこわいおばあちゃんが切り盛りする店だった。
おばあちゃんは、いたずらをする子にはとてもこわいけれど、幸名には、とても優しくしてくれる。
なにより幸名にとって、数少ない、自分の顔と名前を憶えていてくれる大人の一人でもあるのだ。
泥だらけのサッカーボールを抱きしめて、幸名は長いこと、じっと張り紙を見上げていた。
それからおもむろに、踵を返す。
電信柱のある角を右に曲がって、お店の裏手の路地へと進んでいく。
お店以上に年季の入った平屋の前で、幸名は立ち止まる。
少しためらってから、古びたチャイムのボタンをぎゅうと押し込んだ。
ぴんぽん、と音が鳴って。
ずいぶん経ってから、ゆっくりと、玄関の引き戸が開いた。
「どちらさま・・・?」
掠れた声でそう言いながら、小柄な女性が顔を出す。
彼女は、幸名がサッカーボールを手にしていることに気付くと、力なく微笑んでみせた。
「将太の、お友達?」
幸名はこくりと頷いて、少しだけ、身を乗り出した。
「ゆきなです。ひよし、ゆきな」
「・・・・・・ゆきな、くん」
確かめるように、彼女が繰り返す。
聞き覚えの無い名前に、戸惑っているようにも見えた。
「将太に、会いに来てくれたのかな・・・?」
今にも泣き出しそうな顔をして、彼女は言う。
うれしいのか、かなしいのか———大人はよく、わからない。
「・・・どうぞ。あがっていって」
からら、ともう少しだけ戸を開けると、彼女はほっそりとした左手で、ちいさく手招きをした。
黒い、四角の中で。
ほんの数日前まで一緒にあそんでいたともだちが、楽しそうに笑っている。
———笑ったまま、動かずにいる。
少しへたれた座布団の上にすわって、手を合わせる。
将太は幸名よりも、少しだけ背が高い。
だから、目の前の小さな壺の中に彼がいるのだと言われても、いまいちピンとこない。
まほうかな、と思う。
学校の先生は、将太はコウツウジコにあったのだと言った。
フウンナジコだったと。
それから、車には気をつけなさいとも言った。
将太が会った子は、車に乗っていたのだろうか。よくわからない。
ただ漠然と、もう彼と遊ぶことはできないんだな、ということだけは、わかった。
帰り際、ふと幸名は、気になっていたことを将太の母に問いかけた。
「おみせは、いつ あきますか」
玄関の戸をことさらゆっくり開けて、ささやかな庭をそっと覗き込みながら、
彼女は残念そうに、首を振る。
「おばあちゃん、将太がいなくなってから、すっかり元気がなくなっちゃって・・・いつになるか、わからないの」
ごめんね、と、彼女は言う。
幸名が大好きな駄菓子屋のおばあちゃんは、
将太にとっては、血のつながったおばあちゃんだ。
庭の片隅で、芽が出たばかりの朝顔の鉢をぼうっと眺めるおばあちゃんの横顔は、
まるでたましいが抜けてしまったみたいに見えた。
「しょーたがいなくて、さみしいのかな」
少しだけ湿気をおびた夕暮れの風が、幸名のやわらかな髪をふわりと揺らす。
軒下で、ちいさな風鈴が、チリンと鳴った。
「しょーたがいたら、さみしくないかな」
将太が、ここにいたら。
いつもみたいに、ここに。
幸名の手から、ぽん、と、サッカーボールが転げ落ちる。
将太は、おばあちゃんのこと、なんて呼んでたっけ。
いつも、彼は、どんな声で。
どんな、顔をして。
「・・・・・・」
おばあちゃんの顔が、ゆっくりと、こちらへ振り返る。
ぼんやりとしたその瞳が、次第にしっかりとした焦点を結び始める。
驚いたふうに、目を見開いて。
「将太・・・」
つぶやく彼女のしわしわの手を、幸名はぎゅうと握りしめる。
将太ならきっと、こうする。
———ぼくが、しょうたなら。
「ほんと詐欺すぎるわ・・・どうやったらたった5分でそうなれるのよ」
シルエイティのハンドルを乱暴にきって、相楽朋子は溜息まじりにそうごちた。
助手席で雑誌をめくっていた青年が、遠心力に振られて窓ガラスに頭を打ちつける。
衝撃でずれた眼鏡を押し上げる仕草はどことなく、いじめっ子にどつかれた、いじめられっ子にも似ていた。
「きみのその多重人格っぷりは、穂高真城の遺伝なの?」
「・・・ちょっと何言ってるのか分からないなァ」
ダッシュボードに吹っ飛んだ雑誌を再び手に取って、彼は複雑な顔をした。
表紙を飾るのは、国民的女優・穂高真城。
———本名『日吉真白』。
日吉幸名の、実の母親である。
とはいえ息子である当の本人に、その自覚はない。
彼女が幸名の元へ顔を出すのは、数年に一度のペースだし、
そもそも彼女のプロフィールに、子持ち、などというステータスは載っていないのだ。
「・・・あれ、俺、載ってる」
白黒の特集ページを開いて、幸名は少し驚いたふうに声をあげた。
『いま大注目の男の子たち』———そんなタイトルのついた記事の、片隅。
若手俳優部門、アイドル部門と並んで、モデル部門のトップに”Yuna”という名が載っている。
年齢不詳経歴不詳、とにかく謎まみれの、絵画から飛び出してきたような美青年———それがYunaの特徴だ。
顔がいいだけではない。彼が雑誌のグラビアで着用した衣装はすべからく売れる、というジンクスまであって、
今や業界で引っ張りだこの超人気モデルである。
まぁ、その素顔は、ただの冴えない大学生なのであるが。
日吉幸名という人間は、根本的には、空っぽだ。
ゆえに、目の前のひとたちが”期待する姿”を無意識に演じてしまうという、難儀な癖の持ち主でもあった。
結果としてそれが、”モデル業界の人々が必要とする最高の人材”を作り上げることになってしまったわけで。
「・・・騒ぎになる前に、辞める?」
赤信号の交差点に、シルエイティがゆっくりと停車する。
朋子としては、幸名にも真城にも、迷惑をかけることは本意ではない。
幸名は雑誌を閉じると、ううん、と唸った。
「いまの部屋の家賃とかもろもろ支払えるだけの稼ぎは欲しいし・・・もう少し、雇ってもらえると、うれしい」
信号が変わって、車は一方通行の細い路地へと進んでいく。
雑居ビルの地下駐車場へ滑り込んだところで、朋子はサイドブレーキを引いた。
”Yuna”が着ればハイブランドにも劣らない、当たり障りのないファストファッション。
なのになぜか、”幸名”が着ると、あり得ないほど野暮ったく見える。
どこまでが彼の”癖”なのかは分からないが、今はそれがむしろ、良い方向にはたらくような気にさせた。
「じゃあ、また」
ぎこちなく微笑んで、幸名は車を降りる。
その背中を見送った朋子は、ちいさく溜息をついた。